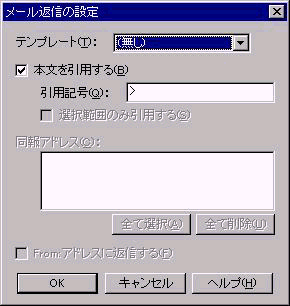
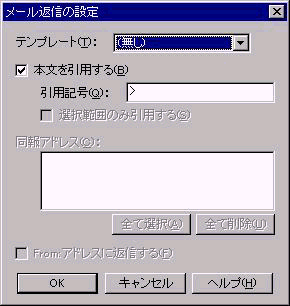
受信したメールに返事を書きたい場合には、新たに新規送信でメールを送ってもよいが、メーラの返信機能を使うと便利なことが多い。返信を行いたい場合には、前節で説明したメール内容を表示させた状態で返信ボタンをクリックしてもよいし、また、郵便受けのフォルダを表示させておき(右側のボックスには受信したメールの一覧が表示されている)、返信を行いたいメールを指定(反転表示)しておいた上で、返信ボタンをクリックしてもよい。
返信ボタンをクリックすると右のようなダイアログボックスが表示される。
上部のテンプレートというのは定形的なメールを書くときに用いるもので、ここでの説明は省略する。
次の本文を引用するという所にはチェックマークが付いていると思うが、ここにチェックマークが付いていると、この後見るように、返信を書こうとするメールには予め相手のメールの内容が引用(表示)される。そのようにしたくない場合には、ここをクリックし、チェックマークを消しておけばよい。
その下の引用記号というのは相手のメールを引用する際にその行頭にここで指定した記号を付けるというものである。通常は始めから表示されている > を用いるのが一般的であるのでこのままでよいと思われるが、別の記号を指定してもよい。
それ以外に付いてはこのダイアログボックスのヘルプボタンをクリックし、ヘルプの内容を見てもらいたい。
多くの場合には、このダイアログボックスで何か指定する必要は無く、そのままOKボタンをクリックすればよいであろう。

特にこのダイアログボックスで指定をせずにOKをクリックすると、右のようなウィンドウが現れる。このウィンドウそのものは新規送信を行ったときと同じものであるが、いくつかの内容が予め書きこまれている。
まず、題名のボックスには元のメールの題名にRe: というを付けたものとなっている。これはそのメールの返信であることを表している。宛先のボックスは元のメールの差出人のメールアドレスとなっている。結局、返信の場合ヘッダについては特に改めて指定する必要が無いということである。ただし、例えば題名を別のものに変えたいというときなどにはヘッダの内容を変更しても構わない。
メール本文のところには、差出人の名前(フルネーム) さんは書きました: という1行の下に元のメールの内容が、行頭に引用を表す>が付けられて書きこまれている(メール返信の設定のダイアログボックスで、特に変更しなかった場合)。引用はこのような形となるので、メールを送る際に、日本語ならば1行、30〜35文字程度としておかないと、非常に見にくいものとなってしまう。
メール本文には自由に文章を挿入したり、付け加えたりすることができる。また、引用した部分を削除することもできる(変更も可能であるが、それはマナーとして止めたほうが良いであろう)。つまり、メール本文の部分は自分が送りたい返信内容となるように自由に使ってよいということである。 完成した返信用のメールを送信する方法等は新規送信の場合と同様である。
受信したメールを別の第三者に送りたいということもある。この場合には転送の機能を使うのが便利である。転送を行うには、返信の場合と同様にして転送のボタンをクリックすればよい。
転送の場合には返信の場合のようにダイアログボックスは表示されずに、いきなりメール送信のウィンドウが表示される。題名は元の題名の前に転送を表すFwd: が付き、宛先の部分は空欄となっている。メール本文は元のメールの差出人 さんのコメントを転送します: という1行の下に、元のメールの本文が(この場合には引用記号を用いずに)並ぶこととなる。従って、宛先のボックスと、必要ならばメール本文に適当に書き加えて送信すればよい。